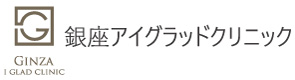再生医療は、けがや病気で損なわれた組織や臓器を細胞レベルで再生・修復します。自分の細胞を使うため拒絶反応も少なく、根本治療の可能性を秘めています。革新的な技術であるがゆえ、高額な費用や長期の治療期間が必要となるケースもあるので注意が必要です。
この記事では、再生医療のメリット・デメリットをはじめ、治療法による費用相場や注意点を解説しています。記事を読めば、再生医療の知識が身につき治療を受けるかの判断ができます。
再生医療とは細胞を用いて組織や臓器を再生・修復する医療技術
再生医療とは細胞を用いて組織や臓器を再生・修復する医療技術です。再生医療は、自然治癒力を高め、より深刻な損傷や疾患にも対応できる技術です。再生医療の核となるのは「細胞」です。私たちの体は、皮膚や骨、心臓など、さまざまな役割を持つ細胞が集まってできています。再生医療では、細胞を巧みに操り、損傷した部分を修復します。
再生医療は発展途上の技術ですが、私たちの未来を大きく変える可能性を秘めています。将来的には、これまで治療が難しかった病気やけがも治せる可能性があります。再生医療は高額な治療費がかかる場合もあり、長期的な効果や安全性の検証がまだ十分でない部分もあります。治療を受ける際には、メリットとデメリットを理解し、医師とよく相談することが大切です。
再生医療のメリット
再生医療は、私たちの体が本来持つ「治る力」を最大限に引き出す、最先端の医療技術です。けがや病気で損なわれた組織や臓器を、細胞レベルで再生・修復することを目指しています。
根本治療ができる
従来の治療は、痛みや炎症を抑えるなど、症状を和らげる「対症療法」に重点を置いていました。風邪を引いたときに解熱剤を飲むのは対症療法の代表例です。熱という症状を抑える治療であり、風邪のウイルス自体を退治するわけではありません。
再生医療は病気の根本原因を取り除く可能性のある治療です。例えば、変形性膝関節症は、加齢や激しい運動などで軟骨がすり減り、炎症が起こって痛みを生じる病気です。従来の治療では、痛み止めやヒアルロン酸注射で痛みを軽減していましたが、すり減った軟骨自体は元に戻りません。再生医療では、患者さん自身の細胞から軟骨を培養し、損傷部位に移植することで、軟骨そのものを再生させます。
再生医療は、心筋梗塞で傷ついた心筋の再生や、脊髄損傷で損傷した神経の再生など、さまざまな疾患の根本治療に期待されています。
体への負担が少ない
再生医療のもう一つのメリットは、体への負担が少ないことです。患者さん自身の細胞を利用することが多いためです。自分の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが低いのです。皮膚移植が必要なほどの重度のやけどの場合、従来は患者さん自身の体の他の部分から皮膚を採取して移植していました。採取した部分にも傷が残ってしまう問題がありました。
再生医療では、患者さん自身の皮膚細胞を培養して移植できるため、健康な皮膚を傷つけることなく治療できます。手術が必要な場合でも、再生医療では内視鏡手術など、体に負担の少ない方法で行われることが増えています。入院期間が短縮されたり、術後の回復が早まったりするなど、患者さんのQOL(生活の質)向上にもつながります。
再生医療のデメリット
再生医療は、損なわれた組織や臓器の機能を回復させるという画期的な治療法ですが、いくつかのデメリットも存在します。デメリットも理解することで、再生医療を正しく選択することにつながります。
治療期間が長い
再生医療では、以下のような段階を経る必要があり、治療完了までに相当な時間がかかります。
- 細胞採取から培養、移植までに数か月を要する
- iPS細胞を使用する場合、細胞の初期化や目的の細胞への分化に時間が必要
- 移植後も体内での機能定着に時間がかかる
- リハビリテーションが必要な場合は、さらに期間が延長
特に高齢の患者さんにとって、この長期間の治療は身体的・精神的な負担となる可能性があります。また、定期的な通院による生活への影響も考慮が必要です。
費用が高い
再生医療は、高度な技術や設備、専門の医療スタッフなどが必要となるため、費用が高額な傾向があります。費用が高いもう一つの理由は、再生医療はまだ新しい治療法であるため、研究開発費や臨床試験の費用なども含まれている場合があるためです。新薬の開発にも莫大な費用がかかるように、再生医療も最先端技術であるがゆえに高額になりやすいのです。
再生医療は健康保険が適用されない治療法も多く、全額自己負担となる場合もあります。高額な費用を負担することに不安を感じる方も多い傾向があります。再生医療を受ける前に、費用について医療機関によく確認し、経済的な状況を考慮したうえで治療を受けるかどうかを判断しましょう。
再生医療の3つの種類
再生医療の3つの種類は以下のとおりです。
- 細胞移植
- 遺伝子治療
- ティッシュ・エンジニアリング
細胞移植
細胞移植は、損傷した組織や臓器に、健康な細胞を移植する治療法です。自分の細胞を使う場合は、拒絶反応のリスクが低いというメリットがあります。他人の細胞を使う場合は、拒絶反応のリスクを考慮する必要があります。拒絶反応を抑える薬も開発されており、多くの患者さんにとって細胞移植は有効な治療法です。白血病の治療では、骨髄移植によって健康な血液細胞を移植します。
細胞の種類や移植方法、拒絶反応への対策など、細胞移植にはさまざまな種類があります。それぞれの患者さんの病状や体質に合わせて、最適な方法を選びます。
遺伝子治療
遺伝子治療は、細胞の設計図である遺伝子を操作することで、病気の原因を根本から治療する方法です。遺伝子は、私たちの体を作るための設計図であり、設計図にミスがあると、さまざまな病気を引き起こす可能性が高いです。遺伝子のミスの修正をして、病気を根本から治すことを目指します。
遺伝子治療は、まだ研究段階の治療法も多いですが、将来的には、がんや遺伝性疾患など、さまざまな病気の治療に役立つと期待されています。正常に機能する遺伝子を体内に導入することで、病気の症状を改善したり、進行を遅らせたりできます。
ティッシュ・エンジニアリング
ティッシュ・エンジニアリングは、細胞やマトリックス、生理活性物質を組み合わせて、体の外で組織や臓器を人工的に作り出す技術です。日本語では「組織工学」と言います。ティッシュ・エンジニアリングは、けがや病気で失われた組織や臓器を再生するための画期的な治療法です。
重度の火傷で皮膚が大きく損傷した場合、従来は皮膚移植が必要でしたが、ティッシュ・エンジニアリングによって患者さん自身の細胞から皮膚を培養し、移植することで、拒絶反応のリスクを減らしながら治療できます。
ティッシュ・エンジニアリングは、歯の再生にも応用が期待されています。歯は、エナメル質や象牙質、セメント質や歯周組織など、さまざまな組織から構成される複雑な器官です。組織を再生するためには、歯髄幹細胞(DPSCs)、脱落乳歯歯髄由来幹細胞(SHED)など、さまざまな種類の幹細胞が研究されています。歯の組織を再生する能力を秘めており、将来、歯を失っても自分の歯を再生できる可能性もあります。
再生医療の費用相場:治療の種類と部位による費用
再生医療は未来の医療として期待が高まっていますが、費用面は多くの方が気になる点です。治療の種類や部位、使用する細胞の種類、医療機関によって費用は異なります。PRP治療やNK細胞療法の相場を解説します。
PRP治療は10〜30万円程度
PRP治療は10〜30万円程度です。患者さん自身の血液から血小板を多く含む血漿(PRP)を抽出し、損傷した組織に注射する治療法です。PRPには組織の修復を促す成長因子が豊富に含まれており、スポーツによるけがや加齢による変形性関節症などで、膝の軟骨がすり減って痛みが生じている場合などに有効です。
自由診療のため医療機関によって価格設定が異なり、治療を受ける部位や回数によっても費用は変動します。複数の医療機関に見積もりを取り、内容を比較検討することで費用を抑えることができます。
NK細胞療法は数十〜数百万円
NK細胞療法は数十〜数百万円の費用がかかります。私たちの血液中にあるナチュラルキラー(NK)細胞を体外で培養し活性化させ、再び体内に戻すことで、がん細胞やウイルス感染細胞などを攻撃する治療法です。
がん治療の一環として、手術や抗がん剤治療、放射線治療などの標準治療と並行して、あるいは標準治療後に行われるケースがあります。NK細胞は免疫細胞の一種で、生まれつき備わっている「自然免疫」において中心的な役割を果たしています。がん細胞やウイルス感染細胞などを見つけ次第攻撃する頼もしい存在です。
高度な技術と設備、専門の医療スタッフが必要となるため、費用が高額になるのは仕方のない面もあります。治療を受ける医療機関や培養する細胞の数、治療回数などでも変わります。事前に医療機関に相談し、費用や治療内容について詳しく確認しましょう。
再生医療を受ける前の注意点
再生医療を受ける前の注意点は以下のとおりです。
- 技術の発展段階:再生医療は発展途上の技術であり、すべての病気に効くわけではない
- 治療法とコスト:治療法によって費用が大きく異なる
- 保険適用外の可能性:多くの再生医療は保険適用外で高額になることがある
- 医師との相談:効果やリスク、副作用などを医師と十分に話し合う
- 過度な期待を避ける:再生医療は万能ではないため、リアルな期待を持つ
再生医療は可能性において魅力的ですが、治療を選択する際には上記の点を慎重に考慮することが求められます。興味がある方は、専門の医師と相談のうえ、納得のいく形で進めてください。
まとめ
再生医療は、損傷した組織や臓器を修復・再生する革新的な医療技術です。拒絶反応が少ないというメリットや、根本治療を目指せる可能性がある一方で、治療期間が長く、費用が高いデメリットもあります。PRP療法やNK細胞療法、iPS細胞を用いた治療などがあり、費用や効果、リスクもさまざまです。
再生医療について正しく理解し、慎重に検討することで、より良い治療選択につながります。治療を受ける際はメリット・デメリットや費用などを医師と相談し、ご自身の状況に合った治療法を選択しましょう。
参考文献
- Qiming Zhai, Zhiwei Dong, Wei Wang, Bei Li, Yan Jin. Dental stem cell and dental tissue regeneration. Front Med, 2019, 13(2), p.152-159
- Geoffrey C Gurtner, Sabine Werner, Yann Barrandon, Michael T Longaker. Wound repair and regeneration. Nature, 2008, 453(7193), p.314-321.